2025年7月30日に、「中央環境審議会循環型社会部会小型家電リサイクル小委員会リチウム蓄電池使用製品の回収・リサイクルワーキンググループ(第1回)及び産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会指定再資源化製品ワーキンググループ(第1回)」が開催されました。
あまりにも長い名称ですので、以降「リチウム蓄電池使用製品の回収・リサイクルWG」と略称いたします。
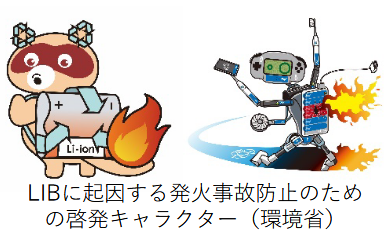 この会合は、経済産業省と環境省が個別に設置したワーキンググループのテーマが同一であるため、両省が共同開催し、活発、かつ効率的な審議が行われることを期待できます。
この会合は、経済産業省と環境省が個別に設置したワーキンググループのテーマが同一であるため、両省が共同開催し、活発、かつ効率的な審議が行われることを期待できます。
個人的には、現在の廃棄物処理処理制度の中で最優先で解決すべき課題の一つが「リチウムイオン電池」と考えていましたので、第1回目のワーキンググループから(YouTubeで)傍聴することにしました。

10年前ならば、東京の審議会場に直接赴き、約2時間の全審議を傍聴しながら、要点を議事録にするという行動が苦も無く取れましたが、最近は加齢のせいか、それとも情熱が不足しているのか、議事録を作成できたとしても、それを翌日にはブログにアップするという手際の良い行動が取れなくなってきました(涙)。
そこで、億劫な作業をAIに代行してもらい、人間は最終アウトプットの調整に専念するという「ザ・DX」を実践すべく、WEB上で評判の高い「PLAUD NOTE」を購入してみました。
そのため、今回はAIの処理能力及び正確性の実験の意味を込めて、速報性だけを重視して関係省庁よりも早く議事録を公開します。
なお、字句等の明らかな間違いは修正しましたが、AIの出力結果をできるだけそのまま掲載します。
文章の正確性については保証できませんので、一文字一句レベルの正確性を重視される方は、正式な議事録の公開をお待ちください。
それでは、PLAUD NOTEで生成された議事録を元に、第1回ワーキングループの審議状況を見ていきましょう。
概要
この文書は、2025年7月30日に開催されたリチウムイオン電池や加熱式タバコデバイス等の回収・リサイクルに関する複数の業界・行政・団体によるワーキンググループ・会議の議事要旨をまとめたものです。制度改正の動向、回収・再資源化の現状、業界ごとの課題、消費者・自治体・メーカー間の連携、情報発信・啓発活動、安全対策、回収量や表示の課題、今後の対応方針などが網羅的に整理されています。最後に、全体のアクションアイテムを一元化して掲載しています。これにより、関係者が現状把握と今後の対応策の検討を効率的に進められる内容となっています。
資料1「議事次第」にあるとおり、今回の会合は「業界団体からの発表」を聞き、委員からその発表内容について質問をしていくというスタイルでした。
発表を行った業界団体は、
一般社団法人JBRC
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会・一般社団法人電気通信事業者協会
一般社団法人日本たばこ協会
一般社団法人日本電機工業会
の4団体でした。
資源循環・制度改正・回収スキームの現状と課題
– 地政学的な不安定化や資源制約の高まりを背景に、資源循環の取り組みの重要性が増しているとの認識が共有されました。
– 2024年5月に資源有効利用促進法が改正され、回収対象製品や制度の見直しが盛り込まれたことが報告されました。
– リチウムイオンバッテリー(特に液体型製品)が新たに指定再資源化製品に追加され、高い回収目標が設定されました。
– 現行制度では、小型リチウム蓄電池やその主要製品のメーカーに回収・再資源化が義務付けられているが、モニタリング体制や回収スキームの構築が不十分で、回収率が低い現状が説明されました。
– 一体型製品の増加により、リチウム蓄電池のみの取り外し・回収が困難となっているため、製品全体の回収促進が課題となっています。
– 法改正により、認定メーカーには廃棄物処理法の特例措置が適用され、回収促進が図られる予定です。
– 指定再資源化製品の追加品目(電源装置、携帯電話用装置、加熱式タバコデバイス、電気掃除機、電気カミソリ等)について業界ヒアリングが実施されます。
AI議事録中の、リチウムイオンバッテリー「(特に液体型製品)」が何に該当するのかが理解できませんでした。
このような形で、資料や口頭説明で言及されていない名称が盛り込まれることがあるので、精査が必要です(笑)。
「資料3:事務局資料」より転載

回収・リサイクルの現状と実績
– JBRCは2004年設立以降、会員数が増加し、全国約7,000の店舗、約9,000の事業者、約6,300の自治体排出場所で回収スキームを展開。
– 2017年からバッテリー単体での回収を開始し、リサイクルマークの有無にかかわらず回収を実施。
– 2024年度の小型充電式電池回収量は510トン、うち一般廃棄物由来は205トン(全体の15%)。
– 回収量は直近で減少傾向にあり、詳細な要因分析や対策は未説明。
– モバイルバッテリーの回収は2017年から約8年間で約30倍に増加し、2024年度まで継続的な回収強化が進められています。
– 携帯電話の回収は全国約8,500店舗で実施、累計5,000万台を回収し、その約7割を再資源化。
– 加熱式たばこデバイスの年間販売台数は少なくとも300万台以上と推計され、全国約1,100店舗で自主回収・リサイクル事業を展開。
AI議事録では「JBRCは」と始まっていますが、上記の4団体の現状をまとめた部分となります。
安全対策・消費者啓発・情報発信
– リチウムイオン電池の誤混入による発火リスクが指摘され、消費者への啓発活動を強化。(JBRC)
– 初期はダンボールで回収していたが、2016年以降は火災リスク低減のため金属缶・樹脂容器(PL缶)へ切替。2023年度からは難燃性樹脂容器への段階的切替を開始。(JBRC)
– 安全対策ハンドブックを全排出場所に毎年配布し、安全な回収体制を徹底。(JBRC)
– 家電メーカーが保有する顧客基盤やデジタルメディア(SNS、LINE、YouTube等)を活用し、消費者への注意喚起・情報発信を強化。(日本電機工業会)
– 自治体によるごみ分別マニュアルやアプリ等の情報提供も重要視されている。(これはおそらく委員の意見)
– リサイクル認知度は約46%、ロゴマーク認知度は19%であり、今後も啓発活動の継続が必要。(情報通信ネットワーク産業協会・電気通信事業者協会)
AI議事録では、「JBRC」「情報通信ネットワーク産業協会・電気通信事業者協会」「日本電機工業会」の取組が一緒くたにまとめられています。
参考に、それぞれの取組主体を括弧書きで明示しておきました。
製品表示・構造・規格の課題
– 小型二次電池使用機器の表示ガイドラインに基づき、製品本体に識別マークやリサイクル表示を実施。
– 表示の視認性向上や識別マークの色分け等、さらなる改善を検討。
– 電池表示(リサイクルマーク、二桁数字、電力量等)の統一・義務化が不十分であり、消費者や回収事業者が危険性を判断しにくい。
– グローバルで共通スペックの製品が増えており、日本独自のマーク導入には対応の遅れや流通在庫への影響など現実的な問題がある。
– 非純正電池による事故増加への注意喚起も強化。
委員の意見及びそれに対する各業界団体の回答がまとめられています。
「電池表示」とは、「資料4-1:一般社団法人JBRC発表資料」で説明があった

リチウムイオン電池の「正極活物質中の最大含有金属」と「再資源化しにくい金属」のコード番号のことです。
業界・自治体・消費者間の連携と今後の方針
– 消費者が電池の種類や排出方法を認識していない現状があり、自治体・業界団体・メーカーによる多角的な情報発信が推進されている。
– 自治体の人員・予算不足に対する業界側の具体的支援策が未定。
– 回収ボックスの設置減少や、コンビニエンスストアを回収拠点としない方針による利便性低下のリスクが残る。
– 業界全体の回収量・回収率の把握が不十分で、マテリアルフロー推計に支障がある。
– 膨張した電池の回収責任が自治体に委ねられており、自治体の負担増加が懸念される。
– 製品設計の目標年度や静脈産業との連携方針が明確でない。
AIによる生成議事録のため仕方がないことなのかもしれませんが、委員の個人的意見が、会合の「最終結論」あるいは「今後の方針」として位置づけられています(苦笑)。
一例を挙げると、
「コンビニエンスストアを回収拠点としない方針による利便性低下のリスク」とは、ある委員が「加熱式タバコデバイス」の回収拠点に「コンビニエンスストアを入れるべき」と指摘しましたが、「日本たばこ協会」から

「たばこ販売店」だからこそ「丁寧な教育を通した安全性の担保」と「豊富な製品知識によるフリーライダー排除対策」が可能なのであり、「コンビニエンスストアのすぐ入れ替わる店員」には、そのようなきめ細かい対応は望めないので、当初からコンビニエンスストアは回収拠点として位置づけていない
と明確な反論がありました。
AI生成議事録を使ってみた感想
以上のように、現時点では、AIが生成した議事録は「概ね正確」ではあるものの、核心に当たる部分に不正確な部分があると言わざるを得ません。
そのため「議事録でござい」と、ノーチェックで議事録として共有してしまうことはまだまだ不安があります。
あくまでも、「流し読み」や「復習用の資料」として、「制度全体の概要を把握する」ことに止めておいた方がよろしいかと思います。
もっとも、そう遠くないうちに、AIが生成した議事録が、ノーチェックのままメディアの報道に載るという事態が起きるような気がします。
否、ひょっとすると、既に起きているのかもしれません。
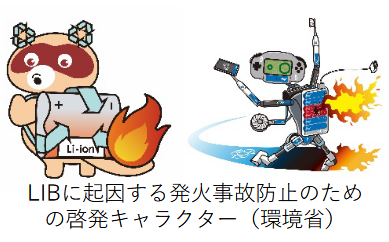
![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)