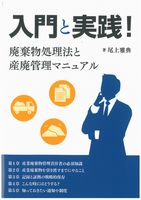財源確保か国益への協力か
清掃工場職員が、市がリサイクルのために回収した小型家電を盗み、転売して利益を得ていたことが発覚し、相模原市から懲戒免職されたという報道がありました。
2024年8月31日付 読売新聞 「小型家電リサイクルで回収の141点をネット売却、49万円利益で懲戒免職…業者売却なら1700円」
小型家電リサイクル法では、使用済み小型家電リサイクル事業で回収した物は全て認定事業者に売却・引き渡すことになっている。ところが、発表によると、男は昨年7月頃~今年5月頃、回収されたデジタルカメラやドライヤーなどの一部を盗み、少なくとも141点をネットオークションに出品、計約49万円の利益を得ていたという。

公務員が、行政が市民から回収した一般廃棄物を盗み、私利を図るために転売をした以上、懲戒免職になるのは当然です。
中古家電をオークションで落札した経験が無いので、中古家電の相場がわかりませんが、
「141点の出品で利益が49万円」とのことですので、ざっと「49万円÷140」で計算すると、1点当たり「約3,500円の利益」となります。
職場に転がっている物品を盗んでいるため、仕入れ原価は「0円」ですので、3,500円が丸々儲けとなります。
厳密には、落札者への配送料が必要ですので、それを差し引くと、「1点あたり3千円の粗利」というところでしょうか。
中古家電という属性からすると、高すぎず、安すぎない、妥当な価格帯のように思えます。
男は、141点を通常通り業者に売却した場合に想定される代金約1700円を市に弁済済みで、49万円近くの利益についても寄付を申し出ているという。
初見では「1700万円って何!?」と驚きましたが、改めて記事を読み直すと、元職員が弁済した金額はたったの「1700円」でした。
小型家電リサイクル法に基づいてリサイクラーに買ってもらう場合は、「中古家電1点100円」という値付けではなく、「1キログラムあたり100円」といった従量制の値付けのようです。
小型家電リサイクラーの場合は、回収した廃家電を転売したりせず、全量を真面目にリサイクルしているものと信じておりますが、本来なら「喜んで買ってくれる人がいる中古品」「まだまだ使える電化製品」を、「資源の有効活用」という名の下に、粉々に破砕をすることが、果たして本当に「環境のために良い」のかどうか?
Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の並びが示しているように、「リサイクル」は一番最後の手段であり、「リデュース」と「リユース」の実施を先に検討する必要があります。
そう考えると、懲戒免職になった男性がしていたことは犯罪ではありますが、「リデュース」と「リユース」を促進していた点においては「環境に優しい」行動だったのかもしれません。
念のため繰り返しになりますが、行政が集めた不用品を、「もったいないから」という理由で清掃工場から運び出すと犯罪になりますので、持ち去りは「ダメ!ゼッタイ!」です。
さて、同じ廃小型家電141点を売却した場合でも、法律的に正しいルートでは「1700円」、直接ネットオークションに出品した場合は「49万円の利益」と、その差は約48万円になります。
「壊れて使用できない廃家電」の場合は、資源回収のためのリサイクルが唯一の選択肢となりますが、
「まだ使用できる中古品」や「売れそうな良品」の場合は、リサイクルに無理矢理回すよりも、ネットオークションに出品し、売却益を自治体の財源とした方が、自治体と住民双方にとってメリットがあると言えます。
「リユース」後に最終的に「廃品」になった時点で、「リサイクル」に回し、資源回収を図ることが、「小型家電リサイクル法」本来の制度理念ではないでしょうか?
読売新聞の報道に戻ると、懲戒免職された男性は、
「10ヶ月間で141点をネットオークションに出品」していますので、
「1月あたり約10点を継続的に出品、発送」していた計算となります。
「ネット販売が本業?」と思いたくなるマメさですが、このマメさを正しい方向に活用していれば、相模原市役所にとっても新しい収益源になったことでしょう。
現在、多くの自治体が、「中古品を欲しいと思う住民」を募るマッチングサービスを利用しています。
このサービス自体は有益ですし、筆者としても何ら異存は無いのですが、自治体自体が回収した不用品を直接ネットオークションに出品するといった、よりアグレッシブな「リデュース」策を採るところが現れてほしいと思っております。
「地方自治法」や「手数料条例」、そして「廃棄物処理法」等々、クリアすべき論点が多数存在することは認識しておりますが、「小型家電なら何でも受入れます」ではなく、「特定のカテゴリーの家電限定」で点検や修理の手間を掛ける余裕があるのであれば、貴重な自主財源となる可能性がありそうです。
要約すると、「リサイクルの一択」ではなく、「売れる物は売る」「売れない物はリサイクルで資源回収する」という、「転売」と「リサイクル」の2つのスキームが併存する形となります。
もっとも、どの地方自治体においても、人手不足が常態化していますので、「そんな面倒な手間を掛けていられないので、最初から小型家電リサイクル法の処分ルートに全量回す」というところだと思います。
しかし、万に一つの可能性かもしれませんが、首長の考えと事務方の考えが一致し、上記の趣旨に賛同していただける自治体が現れないとも限りませんので、あえて愚説を開陳させていただきました。
« 家電リサイクル実績(令和5年度) 労働災害における「アナフィラキシーショック」への備え »
タグ
2024年9月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news