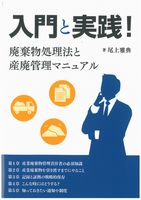経団連の2024年度規制改革要望
2024年9月17日付で、一般社団法人日本経済団体連合会から「2024年度規制改革要望」が公表されました。
一般社団法人の「要望」であり、この内容が法律改正にそのまま適用されるわけではありませんが、2025年から議論開始が目される「廃棄物処理法改正」にも影響を与えそうなタイミングですし、実際に過去の経団連の規制改革要望の一部が「廃棄物処理法改正」に取り入れられた経緯もありますので、少し遅くなりましたが、当ブログでも紹介させていただきます。
Ⅲ. 2024年度規制改革要望【新規】
「2.環境」
No.18. 使用済みの靴の再資源化促進に向けた制度整備
No.19. 消費者から回収した再資源化目的の廃棄物に関する輸出規制緩和
No.20. プラ新法での自主回収・再資源化に際しての再委託の容認
No.21. 排出場所と同一敷地内での廃棄物発電事業等の容易化
No.22. 親子会社間における廃棄物の保管・委託等の一体的推進の容易化
No.23. 店頭回収されたペットボトル等の効率的な収集運搬の加速化
No.24. 小型家電リサイクル法の認定に係る登録管理項目の一部緩和
No.25. 原子炉関連技術の役務取引許可に関する規制緩和
2024年度は、「環境」関連では8項目が挙げられていますが、そのうち、「No.25」は「外為法」に関係するものですので、「廃棄物リサイクル関連法」に関する要望としては7項目となります。
上記のうち、実現可能性が一番高く、環境省からの通知の発出だけで日の目を見そうなものは、
No.22. 親子会社間における廃棄物の保管・委託等の一体的推進の容易化
<要望内容・要望理由>
事業者が産業廃棄物の処理を自ら行う場合、廃棄物処理業の許可は不要である一方、処理を他に委託する場合には、委託先は処理の業許可を得ている必要がある。許可制度を設け、許可基準に適合する事業者が廃棄物処理を行うことで、生活環境保全上の支障が生じる可能性や不法投棄等の不適正処理を未然に防止している。しかし昨今、経営効率化の観点から企業の分社化等が進む中、一つの事業者であったものが、同一敷地内で親会社と子会社に分かれているケースが出てきている。こうした場合、従前(親会社と子会社に分社化される前)と排出や委託等の実態が変わらないとしても、二つの事業者に分かれることで廃棄物の保管や処理委託等を個別に実施する必要があり、事業者側の負担となっている。
そこで、廃棄物処理法の基準等を満たし、1.同一の敷地内かつ子会社の発行済株式の総数を保有する(100%の親子会社関係等、一体的な経営を行っている)こと、2.排出事業者責任は親会社にあること、もしくは親子会社間でそれぞれに共有したうえで、親会社が同一敷地内の子会社の廃棄物を集約して保管・委託等を可能とすることで、事業者側の実務負担をできるだけ効率化すべきである。
これにより、適正処理の確保に係る社会全体のコストが下がることが期待される。
<根拠法令等>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条、第11条、第12条の7
ではないかと考えています。
私見ではありますが、「共同集荷場所(=産業廃棄物保管場所)の提供」と「産業廃棄物管理票の(共同)交付」については、平成23年3月17日付「産業廃棄物管理票制度の運用について」を改定すれば、法律改正をするまでもなく、「行政解釈の変更または明確化」で上記の内容を実現できるのではないかと思っています。
ただし、上記の通知では、「委託契約書(委託基準)」に関する言及はほぼされていませんので、経団連の要望内容に基づいた通知の改定をする場合は、別項目で「親会社が同一敷地内の子会社の廃棄物を集約して保管・委託等を可能とする」旨の説明を書く必要があります。
 もう一つついでに私見を述べさせていただくと、テナントビルから発生した廃棄物の排出事業者は、「各テナント」ではなく、「テナントビルの管理者または所有者」の方が合理的と思っています。
もう一つついでに私見を述べさせていただくと、テナントビルから発生した廃棄物の排出事業者は、「各テナント」ではなく、「テナントビルの管理者または所有者」の方が合理的と思っています。
個別のテナントごとに処理業者と契約をさせるという現状(?)は、テナントと処理業者の双方にとって手間が掛かりすぎるだけだからです。
次の規制改革要望では、「テナントビルで発生した廃棄物の排出事業者」について、経団連から是非声を上げていただくことを期待しております。
« 「移動式がれき類等破砕施設」に関する特例措置 市町村性善説の持続可能性 »
タグ
2024年11月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news