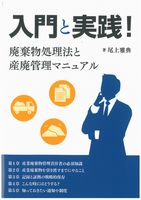「昆虫の養殖」で産業廃棄物処分業許可を取得できるか?
昨年の夏ごろから個人的に注目している研究の続報が入りました。
2025年4月19日付 読売新聞 「ハエ幼虫に生ゴミ食べさせ、フンを農作物肥料に…「価値付けられればゴミではなくなる」」
給食センターなどから出る生ゴミをハエの一種「アメリカミズアブ」の幼虫に食べさせることで食品廃棄物を減らす試みに、山形大農学部の佐藤智准教授(52)(応用生態学)が取り組んでいる。育った幼虫を家畜などの餌にし、さらに幼虫のフンは肥料になる。同大では、フンから作った農作物肥料の試験販売も始まっている。
アメリカミズアブに大量の食品廃棄物を食べてもらうことで、食品廃棄物処分のみならず、幼虫とそのフンも有効活用できるという夢のある研究です。
夢ではなく、実証研究段階は既に終え、ここから技術や製品の普及段階に入る段階と思われます。
山形大学の佐藤教授の研究には大きな期待を寄せていますが、この技術を廃棄物処理業に生かす手段はないものかと考えてみました。
誰もが真っ先に考えるのは、「アメリカミズアブの幼虫を用いた食品廃棄物の処分」だと思います。
しかし、大変残念なことですが、廃棄物処理法に基づく「処分業許可」の対象にはできません。
その理由は、
廃棄物処理法第14条第10項
都道府県知事は、第6項の許可(処分業)の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
廃棄物処理法施行規則第10条の5
法第14条第10項第一号(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(6)その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
と、産業廃棄物処分業の場合は、「産業廃棄物を処分するための施設」が必要であると定めているからです。
「アメリカミズアブの幼虫」は、産業廃棄物処分に適する「処理施設」ではありませんので、「幼虫1万匹に食品廃棄物を食べさせます」では、処分業許可の取得ができません。
「1日あたり5トン」といった処理能力の算定もできませんし。
過去、悪名高い「豊島不法投棄事件」では、1978年に香川県によって「ミミズ養殖による土壌改良剤化処分業のための汚泥処理」という内容の許可が出され、その後の不法投棄の端緒となったことがあります。
※ただし、1978年当時は上記の施設基準はありませんでした。その後、豊島不法投棄事件等の発生を端緒とした平成3年度の廃棄物処理法改正の一環で、施設基準が創設された経緯があります。
 「アメリカミズアブで処分業許可が取れなくて困っている」という声が聞こえてこないので、特に問題にはなっていませんが、国策として「昆虫の養殖」を進めていく場合は、環境省ではなく、農林水産省が特別法を作り、振興を図っていく必要がありそうです。
「アメリカミズアブで処分業許可が取れなくて困っている」という声が聞こえてこないので、特に問題にはなっていませんが、国策として「昆虫の養殖」を進めていく場合は、環境省ではなく、農林水産省が特別法を作り、振興を図っていく必要がありそうです。
廃棄物処理法で議論をしようとしても、「施設じゃないので許可できない」で終わってしまうからです。
アメリカミズアブの幼虫は、肥料と飼料の両方で活用できる有難い資源ですので、有効に活用しない手はありません。
なお、アメリカミズアブと「アメリカ」が付けられていることから分かるように、元々は北米や中米にいた昆虫です。
日本には1950年代に侵入し、北海道を除く各地で生息しています。
幼虫は人間にとっての不要物を爆食してくれますが、成虫のアメリカミズアブには口が無く、餌を食べない(卵は産む)というはかない生き様です。
「便所バチ」という名称の方がなじみ深い人(筆者を含めて)が多いかもしれません。
« 「環境管理(2025年3月号)」に寄稿いたしました 汚物は消毒? »
タグ
2025年4月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:基礎知識