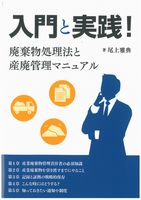理論武装のすゝめ
許可業者たる者、自社の存立にかかわる状況下では、行政と対等に渡り合えるように、行政手続法の基礎知識を身に着けることが不可欠、と痛感させられた報道がありました。
2024年5月13日付 RKB毎日放送 「突然違う業者がし尿収集 戸惑う住民に業者も「『許可を取り消すぞ』と言われるのが怖い」 一部事務組合の不透明な決定」
報道の前段は、
「複数の市町が参加した一部事務組合が、急に各業者のし尿回収エリアを変更し、何も知らされていなかった住民側に混乱と困惑が生じている」というものです。
回収エリア変更の是非については、背景事情がまったくわかっておりませんのでこれ以上言及しませんが、非常に気になったコメントが2つあります。
まず1つ目が
(組合長=町長のコメント)住民の戸惑いについて「それのないように業者には徹底しています。許可をやっていますから、責任を持ってやりなさい」と伝えたとして、業者任せにしていると説明しました。
実際には、一部事務組合から業者に対し、文書等でもっとソフトな指示をしていた可能性もありますが、今のご時世で、「許可をやっている」という居丈高な物言いはいただけません。
「許可」とは「行政が恣意的に与える恩恵」ではなく、「申請に基づき一般的禁止を解除する行為」に過ぎないからです。
「どの言葉を選択するか」に、その人の価値観や信条を見て取ることができますが、令和の現代日本で、「許可を出してやっている」という公的な発言はなかなか聞けるものではありません。
2つ目が、本日の主題でもありますが、
業者は組合長から許可を受ける立場で「意見すらできない」と証言しています。
し尿収集運搬業者関係者「言うこと聞かないと『もう許可を取り消すぞ』と言われるのがもう、やはり怖いですよね。許可取り消しになると仕事ができなくなるので。ちょっと反発すると『許可取り消すぞ、許可欲しくないか』とかそういう感じですね」
「行政手続法」という国会で制定された正式な法律を超越したオカルトチックな論理が展開されています。
まず、業者としての実感であり、口頭コメントという性質上正確性に欠けることは致し方ありませんが、
「組合長個人が中世教皇のように個人として許可を出している」わけではなく、許可主体はあくまでも「一部事務組合」です。
 個人を必要以上に恐れ、敬遠すると、ハリーポッターシリーズの「名前を呼んではいけないあの人」のように、その個人を実体以上の巨大な偶像へと肥大化させ、「対等に渡り合おう」という気概を持つことを自ら放棄することにつながりますので、現代の日本国民及び事業者としては、やらない方が良い行動と思います。
個人を必要以上に恐れ、敬遠すると、ハリーポッターシリーズの「名前を呼んではいけないあの人」のように、その個人を実体以上の巨大な偶像へと肥大化させ、「対等に渡り合おう」という気概を持つことを自ら放棄することにつながりますので、現代の日本国民及び事業者としては、やらない方が良い行動と思います。
また、「交渉相手の力量や限界を正確に把握する」ことが、交渉に臨む前の基本となりますので、少なくとも、交渉相手の「業務内容」「職責」「限界」については、イメージではなく、成文化された根拠を確認しておきたいところです。
今回のケースで言うと、事業者が把握すべき情報は、一部事務組合の「成立根拠」と「所掌事務」、そして「廃棄物処理法の関連規定(第7条その他)」となります。
さて、ここからようやく本日の本題に入りますが、
「言うこと」、すなわち「何らかの行政指導や要請」に従わないという理由で、一般廃棄物収集運搬業の許可を取消すことができるのかという話になります。
多くの方がご存知のとおり
行政手続法第32条(行政指導の一般原則) 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
とされておりますので、行政指導に従わないという理由で許可取消をすると、行政庁の違法行為となります。
ただし、先の報道で登場した「言うこと」が、単なる行政指導ではなく、「一般廃棄物収集運搬の委託契約に基づく債務履行を求めるもの」、あるいは「業者の違法状態の是正を求めるもの」であった場合は、業者側に「契約違反」や「法律違反」が発生する可能性がありますので、その場合は「契約解除」や「許可取消」につながる場合もあります。
ゆえに「(組合側の)言うこと」が何だったのかが重要なポイントになりますが、業者に法律違反があれば即時に許可を取消せるわけではなく、廃棄物処理法では許可の取消要件が厳格に定められています。
廃棄物処理法第7条の4(許可の取消し) 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
- 一 第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに該当するに至つたとき。
- 二 第七条第五項第四号リからルまで(同号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 三 第七条第五項第四号リからルまで(同号ホに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 四 第七条第五項第四号イからトまで又はリからルまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
- 五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
- 六 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
要約すると、市町村長が一般廃棄物処理業の許可を取消さねければならないケースは、
事業者が
・欠格要件に該当した場合
・重大な廃棄物処理法違反をして、情状が特に重い場合
・事業停止命令に違反した場合
・不正の手段を用いて処理業許可を受けた場合
となります。
あとは、「必ず取消し」ではなく、「許可を取消すことができる」ケースとしては、
事業者が
・事業の用に供する施設または事業者の能力が許可基準に適合しなくなった場合
・許可条件に違反した場合
と、2つの要件が限定列挙されているのみです。
いずれの場合でも、「行政指導に従わない事業者の許可は取消し可能」とは書かれていませんし、そう読むこともできませんので、「組合長」や「一部事務組合」を「名前を呼んではいけないあの人」レベルで恐れる必要はまったくありません。
行政側に住民の希望や効率的な行政運営のアドバイスができる当事者は、実際にし尿や廃棄物の回収に携わり、地域の実情にもよく精通している各地の一般廃棄物処理業者しか無いと思いますので、これまで培ってきた信用や実績に自信を持ち、行政と対等な意識で渡り合っていただくことを期待しております。
« 第18回「第18条 廃棄物処理法の特例」再資源化事業高度化法 第19回「第19条 指導及び助言」再資源化事業高度化法 »
タグ
2024年5月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news