農業廃棄物の解決手段
前回の「農家の産業廃棄物委託基準」の続きとなります。
「農家に著しい負担とならず、社会的にももっと合理的な解決策」に関し、愚考した結果を記していきます。
結論を先に書くと、
農家にとって完全にストレスフリー、かつ手間フリーという夢のような解決手段は存在しません。
「農協が提供した共同集荷場所に農家自身で持ち込む」場合以外は、基本的に、農家は「排出事業者」として、「委託契約書」や「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の運用が不可欠となります。
まず、前提条件として、農業廃棄物の弱点は2つあります。
第一に、「軽量でも容量としてはかさばる物が多い」
第二に、「土や泥等の汚れが付着することが多い」 という制約です。
「資源として売る」ことを目指す場合は、土や泥が付着しないように、プラスチック容器などを誰かが洗浄する必要があります。
そこで、まず決めるべきことは、「農家において水でどこまで洗浄してもらうか」という基準になろうかと思います。
「水をかけて洗浄なんてやってられるか!」という人が大半の場合は、「破砕」や「焼却」をし、処分場で埋立て処分をしていくしかありませんので、今までどおりの処分方法を踏襲していくこととなります。
逆に、「コンテナの泥落としくらいならやるよ」という人が多い場合は、
・プラスチックの材質を選別し、
・プラスチック原料として買い取ってくれる相手が見つかり、
・買取り業者が求める品質にプラスチック廃棄物を加工できるのであれば、
場合によっては、「処分費(コスト)」ではなく、「売却益(利益)」が発生する可能性もあります。
※実際には、回収量や回収場所からリサイクル先までの距離の問題で、「買取額」よりも「運賃(送料)」の方が高くなることがほとんどです。
先述した第一と第二の制約上、農業廃棄物の場合、
農家 → 中間処理業者 という直接取引ルートを取ると、コスト面で無駄が生じることが多くなります。
そのため、
農家 → 農協その他の第三者で集約処理 → 買取り業者
という商流が不可欠と考えられます。
もちろん、上記の「農協その他の第三者」は、各農家が発生させた産業廃棄物処理を受託することになりますので、産業廃棄物処理業の許可取得が必須となります。
手ばらしだけで解体できるのであれば、「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)」の許可で操業可能ですが、この場合、最終的に積替え保管場所から処分業者のところに産業廃棄物が行くのであれば、「農家と産業廃棄物処分業者との契約」が必要となります。
農協等が廃プラスチック類破砕機を設置し、産業廃棄物処分業の許可を取得する場合は、農家にとっては農協等だけが契約の相手方となりますので、契約書と産業廃棄物管理票の運用はそれほど難しくありません。
実際、地域によっては、ビニールハウスシートの集約処分等を目的として、農協が処分業許可を取得し、農家が排出した産業廃棄物を引き受けている実例が既にあります。
残りは業許可取得のための現実的な課題ですが、それは大別すると3つあります。
第一に、「そこそこの広さがある敷地を確保できるかどうか」
事業用地の確保可能性が無いのであれば、どうしようもありませんので。
第二に、「機械や建屋を設置するための資金があるかどうか」
既存の建屋があり、そこで産業廃棄物を保管し続けることが可能であれば、機械を置かずに、「積替え保管」事業を行うこと自体は可能です。
この場合は、本当の意味での「集荷場所を提供」することになるため、事業内容としては理解しやすいかと思いますが、先述したとおり、農家と産業廃棄物処分業者との契約は不可欠です。
廃プラスチック類の破砕機の場合、中古市場で出回っていることも多いため、運がかなり良ければ、安価で理想的な設備を購入できるかもしれません。
ただし、リサイクル原料として、中間処理後に売却できる品質に産業廃棄物を加工したい場合は、機械メーカーと協議の上、最適な設備を導入した方が良いだろうと思います。
第三の課題は、「人員を配置できるかどうか」です。
昨今の社会情勢においては、これが一番のネックかもしれません。
事業として産業廃棄物処分業を行う以上、最低限の人員配置は必須となります。
いずれも、悩ましい現実には違いありませんが、「土地と建屋は既存のものを利用可能」という場合は、かなりハードルが低くなりますので、実現可能性はより高くなります。
人員については、フルタイムの雇用ではなく、「週2回の稼働日だけのパート雇用」という形でも、廃棄物処理法上は問題ありません。
農協等の地元に根ざした組織が処理業許可取得を目指す場合、一般的なよそ者企業が乗り込む場合とは異なり、地元の反対はほぼ出ないと思われますので、上記の課題をクリアできている場合は、かなり円滑に業許可を取得できます。
それでも不安に思う場合は、是非当事務所にご相談ください(笑)。
« 農家の産業廃棄物委託基準 起きるべくして起きた不法投棄 »
タグ
2024年8月2日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
カテゴリー:news
トラックバック&コメント
トラックバック
コメント





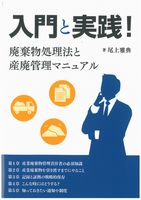
いつも楽しく読ませていただいております。
2年近く前の話です。協力いただいている千葉県のリサイクル業者が新たに「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)」の業許可を申請しようとしましたが、行政書士から「千葉県では積替え保管の許可は新規には下りませんよ。」と言われ、結局、収集運搬業のみになってしまった、という話を聞きました。
業者も食い下がったようでしたが「下りないものは下りない。」というようなことを言われたようでした。
その背景の詳細はわかりませんでしたが、千葉県で過去に保管基準違反や、業者の倒産(破産)での代執行が頻発していて、県が許可を下ろさなくしたのかな、と思いました。
全国的にはどうなんでしょうか? 後学のためにコラムで御教授いただけると幸いです。
今回のコラムを読んで、そのことを思い出しました。
M.O様 コメントいただき、ありがとうございます。
千葉県に積替え保管許可を申請したことが無いので、真偽のほどはわかりませんが、
千葉県HPで「指導要綱」を参照したところ、「積替え保管許可の新規申請は認めない」という趣旨の記載はありませんでした。
そのため、手続き的には、新規申請は禁止されていないものと理解しております。
今からでも積替え保管許可申請は可能と思われますので、取引先リサイクル業者の方に教えてあげるとよろしいかと思います。
私が直接扱った案件では、積替え保管許可はしないという自治体はありませんでしたが、
一昔前、そういう運用をしている自治体の噂は聞いたことがあります。
※千葉県ではありません。